![]()
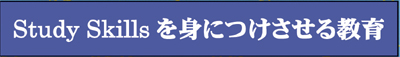
| 第21回 個人課題研究 : 田代ゼミ27 回生の場合(その2) |
| 高校2年次に1年間かけて自分の関心のあるテーマを研究し、まとめる個人課題研究。開校以来30年間続けている取り組みです。 この個人課題研究は、高校1年の1月にテーマを決めて1年間研究を続けるため、その間に興味関心が変化することも当然あります。また、論文を書き上げた後に「自分にはやっぱりこの分野は向かない」と感じて進路変更をする場合もあります。私の感覚だと約3割の生徒は、実際研究をしてみて自分の希望や適性と合わないと感じ、変更しているように思えます。勿論、「それでいい」のです。立派な研究論文を完成させることが第一目標ではなく、自分の将来の希望分野を実際に研究し、専門家に触れ、体験しながら考えることを重視しているので、「自分に合わない」ことがわかることも大事な目的なのです。この27回生の例を紹介します。 No.37のUさんは最初医学に関心があり、高齢化社会の問題と、プロジェリア患者が通常の10倍の速さで老化してしまう早老症をテーマにしました。老化のメカニズムと早老症、特にウェルナー症候群の遺伝子異常について実に精力的に研究し、ウェルナー症候群の劣性遺伝子に関する仮説やDNAヘリカーゼを多く含んだ抗ガン剤を投与するという仮説を考察し愛媛大学の三木哲郎教授からアドバイスをもらって立派な論文を仕上げました。 No.6のDさんも最初は医学希望でした。論文タイトルは「川崎病における原因究明と治療展開」ですが、サブタイトルは「溶血性連鎖球菌説を主とする原因諸説の是非とガンマブログリン大量投与療法不応例に対する新治療法の研究」です。小児急性熱性皮膚粘膜リンパ節症候群、通称川崎病患者は年々増え続けているにもかかわらず、未だ根本治療の方法、それどころか原因すら確定されていない難病です。この難病に真っ向から向かい合い、徹底的に文献研究をし尽くし、原因については溶血性連鎖球菌外毒素説をとり、遺伝性はなく人種に関係するという仮説をたて、治療法については大腸菌で培養した人工抗体でガンマグロブリンで治療し、不応例に対してはステロイドやインフリキシマブを併用する仮説をたてました。アドバイスもこの難病の命名者である日本川崎病研究センター長の川崎富作先生から得、非常に高く評価してもらいました。 まだまだ、一人一人にそれぞれのドラマがあり、味わいのある研究があります。 自分の脂肪が気になったKさん(No.18)は脂肪細胞のメカニズムと小さくする方法を研究し、東邦大学薬学部に進学しました。 暴力団山口組に興味があり、山口組を訪問したいという希望をやめさせて司法の立場からの暴力団の研究にさせて、明治大学法学部に進学したE君(No.10)。 温暖化防止のために化学的に二酸化炭素を水素化したりメタノールに変化させる方法の実用性を悪戦苦闘して研究したM君(No.29)は筑波大学理工学群に進学しました。 論文を半年で書き上げ、UWCアドリアティックに留学し大活躍しているVさん(No.38)の話はそのうち紹介します。 とても全員をこの紙面では語り尽くせませんが、彼らとともに行うゼミがいかに魅力的か想像できますか。
質疑応答では、自分の専門外の発表に対してはできるだけ素朴な質問をしなさいと言っています。素朴な質問をするシロウトに、わかりやすく端的に答えられる人が本当にわかっている人だと。だから、自分がいかにわかっていないかを教えてあげるためにも素朴な質問をしてあげよう、と話しているのです。また、研究分野が似ている者同士の場合は情報交換も含めて深い質問をするようにアドバイスしています。 ゼミでは司会(座長)の役割も教えています。司会はただのタイムキーパーや交通整理ではない。発表が充実したものになるように気を配り、誰も質問者がいなかった場合は関連する研究分野を持つ生徒に答えやすいように誘導を加えて指名するとか、司会自ら質問をする役割を与えます。そうすると、司会は事前にレジメを読んでおく必要がありますし、発表も必死に聞くようになります。将来の学会発表に備えるだけでなく、プレゼンテーションスキルに関係してくる大事なStudy Skillsです。 ☆ このような個人課題研究田代ゼミ、わくわくする100分間です。どうぞ見学にいらしてください。 |
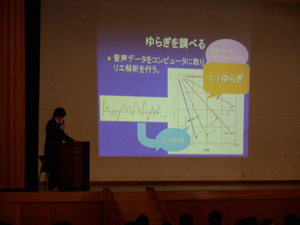
| 表-1 27回生 個人課題研究 田代ゼミ生の研究テーマ |
||
| No |
著者 |
研究テーマ |
1 |
A君 | 線維芽細胞増殖因子FGFについて |
2 |
B君 | ガンの免疫療法 |
3 |
Aさん | ガンの遺伝子治療におけるp53を用いた治療 |
4 |
Bさん | オジギソウについて |
5 |
Cさん | 住宅地と水田の適正配置によるヒートアイランドの緩和 |
6 |
Dさん |
川崎病における原因究明と治療展開 |
7 |
Eさん | 日本人の誇り |
8 |
C君 | 今の日本におけるホスピスの発展と小児ホスピスの実現 |
9 |
D君 | サヴァン症候群の発症原因について |
10 |
E君 | 暴力団対策法と現代のヤクザ問題 |
11 |
Fさん | アレルギーとこれからの治療 |
12 |
Gさん | 地球温暖化の検証および食糧問題解決への自分の仮説 |
13 |
Hさん | MAPC実用化への問題点と解決法 |
14 |
Iさん | 日本のODAの問題点と改善のための仮説と考察 |
15 |
F君 | 新型インフルエンザウィルス〜問題点とその解決策〜 |
16 |
G君 | 公訴時効の正義性を考える |
17 |
Jさん | 自分の犬の問題行動を動物行動学から考える |
18 |
Kさん | 脂肪細胞を小さくする |
19 |
Lさん | 動物の寄生虫 |
20 |
Mさん | ペンギンの生態と歴史について |
21 |
H君 | A〜G型肝炎の特徴を理解し、難治性のB型・C型について考える |
22 |
I君 | 腫瘍エスケープ機構を考慮に入れた新免疫療法 |
23 |
J君 | 糖鎖科学の研究の現状と疾患に対する有用性 |
24 |
K君 | 日本銀行と欧州中央銀行の比較 |
25 |
Nさん | 日米安全保障条約および事前協議制と核に関する密約 |
26 |
Oさん | 体性幹細胞による再生医療 〜体性幹細胞を用いたティッシュエンジニアリングによる人体再生と体性幹細胞の可能性〜 |
27 |
Pさん | テーラーメイド医療〜個人差の原因である遺伝子多型と解析法〜 |
28 |
L君 | ニューロン新生メカニズムを利用した末梢神経障害治療 |
29 |
M君 | 水素化・メタノール化による二酸化炭素の削減 |
30 |
N君 | 希望の癌治療 |
31 |
Qさん | 動物実験の現状と代替法の可能性 |
32 |
Rさん | 児童虐待が脳に及ぼす影響〜海馬の萎縮に対する新療法を考える〜 |
33 |
Sさん | 有機ELディスプレイについて |
34 |
O君 | リスクをどう回避するか |
35 |
P君 | 漢方と西洋医学の併合 |
36 |
Tさん | トランスジェニック技術の開発 |
37 |
Uさん | 早老症について |
38 |
Vさん | 世界的教育援助ネットワークを考える |
39 |
Wさん | イラク戦争問題と復興人道支援を世界的視点から考える |
|
筆者 : 自己紹介 |
|||||
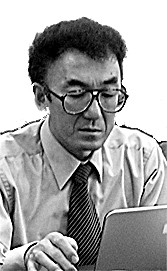 |
茗溪学園中学校高等学校 教務部長 広報・入試係 化学の教師です。 茗溪学園では前向きで明るく逞しく積極的な青年が育っています。 「有名大学に行きたいから勉強する」のではなく、「中学・高校時代にいろいろな事に挑戦し、失敗し、考え、自分を探して、自分で自分の将来をみつけ、自分で歩んでいく。その方向が地球を救い、人類の未来を拓く方向であってほしい。」そう考え、支援するのが茗溪学園の教員の役割です。 海外生・帰国生が自分の力で自分の未来を切り拓いてきた経験はここで開花します。これまでたくさんの帰国生が、夢を追いながら進学していく姿を見て応援してきました。 よろしくお願いします。 茗溪学園の「Study Skills」やカリキュラムについてのご質問は、 |
||||