![]()
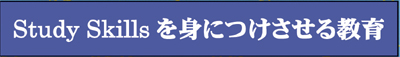
| 第20回 個人課題研究 : 田代ゼミ27 回生の場合(その1) |
| これまでのこのコラム(その2・6・7・8・9・18)で度々紹介してきました、高校2年次に1年間かけて自分の関心のあるテーマを研究し、まとめる「個人課題研究」。開校以来30年間続けている取り組みですが、その後もますます充実しています。 今回は、今年の3月に卒業した27回生のうち、「田代ゼミ」の生徒たちのエピソードをお知らせします。
個人課題研究 この個人課題研究は茗溪学園が独自に設定したいわゆる「学校設置科目」です。今でこそ総合学習として中学・高校とも必修科目として学習指導要領に織りこんでありますが、Study Skillsの獲得を教育目標の根幹に置いている茗溪学園では30年前から必修科目として高校2年に設置しています。テーマに関し、教師から誘導・強制することはいっさいなく、純粋に自分の研究したいテーマを自分自身で探求する、本当の問題解決能力の育成プログラムであり、松本編集長がよく仰るIndependent Thinker となるための最終プロセスとして位置づけています。従って、生徒も教師もこの取り組みに注ぐエネルギーは莫大なものです。 さて、生徒に自由にテーマを設定させると「~という形で世の中(の人々)の役に立ちたい」と将来を発想してテーマを絞っていきますから、社会的なテーマと科学的なテーマが多くなります。この取り組みでは生徒は指導教師を自由に選べますから、どうしても社会科と理科の教師に希望生徒が多く集まります。そこで、社会と理科の教師は個人課題研究の時間として確保されている土曜の3・4時間目(本校は6日制です)はできるだけ授業を入れないように時間割を工夫します。それでも、例えば私を指導担当として希望した生徒は30名近くなるため、とても個別指導では対応できません。そこでここ15年くらいはゼミ方式で指導しています。この2時間内に一人3分で発表し、司会の生徒(「座長」という役職です)のもとで質疑応答を入れながらディスカッションしていきます。最後に私から全員に短くコメントしていき、全体に次回の課題を提示するという方法です。 この年度のゼミ員全員の研究テーマを紹介すると表1のようになります。いくつかの例を紹介します。
実例紹介 No.31のQさんはデュッセルドルフ日本人学校から海外生特別選抜で合格した高校入学生です。ドイツはペットに関する飼い主の義務が徹底していて、日本のように簡単にペットを購入し簡単に捨ててしまうことができません。動物を愛するQさんは、動物が犠牲になる動物実験をなくせないか調べていくうちにドイツの代替法に注目、日本でなぜ代替法を適用できないかを考察しました。研究のアドバイスをもらった日本動物実験代替法学会の教授から、研究成果を学会の第20回大会の高校生の部で発表することを勧められ、その年の12月に発表しました。Qさんは動物を救う獣医になることを目指し、麻布大学獣医学部に進学しました。 No.16のG君は法律に興味のある元野球部の生徒で、時効の成立している28年前の殺人事件の犯人が自首してきたニュースから時効制度に関心を持ち、研究を始めました。G君は主に海外の時効制度と比較する方法をとり、彼自身のカテゴリーで「大陸法系(独・仏)」と「英米法系」に分類し、独自の視点でその背景となっている思想を整理して日本の公訴時効制度の今後の進むべき方向に仮説をたてて論文化しました。G君は東京大学文科Ⅰ類に進学しました。 No.14のIさんは日本のODAが巨額の援助をしているのになぜこんなに批判されるのかという疑問から問題点を探る研究をしました。特に対中支援に焦点を絞り、北京・秦皇島鉄道拡充事業の例を研究し、ODA大綱違反や事前調査の不足の問題点を指摘、解決のための仮説を提案しました。研究のアドバイスは慶応義塾大学総合政策学部草野厚教授からもらいましたが、進学は筑波大学国際総合学群を選びました。 No.7のEさんはちょうど研究の始まった高校1年の1月から1年間、オーストラリアに留学しました。将来国際的な仕事を希望していた彼女は、海外で活躍する日本人として何を誇りにできるかということをテーマにしたいと希望していました。留学中は電子メールで私と連絡を取り、せっかく海外にいるのだからそこでできる研究方法として、留学先のオーストラリアの高校生が日本人に対してどのようなイメージを持っているのかを面接調査してくること、現地に暮らす日本人が何を誇りにしているかをインタビューしてくることを試みました。しかし留学先はヴィクトリア州の大草原の中の村。日本人はほとんどいないため、たまに出かけるときのバスに乗り合わせた日本人らしき人にアタック。帰国後、締め切りを延長してもらい、文献研究を付け加えて論文化しました。進学は東京大学文科Ⅲ類にしました。 No.23のJ君は生命科学に興味があり、高校生ではほとんど思いも及ばない糖鎖科学に注目しました。実は私もよく知らなかった分野で、彼のゼミでの発表で目から鱗が落ちる思いだったのですが、癌もインフルエンザを含む大抵のウィルス病もその疾患メカニズムのどこかに糖鎖が関与しており、逆に糖鎖を研究することでそれら難病の治療の方法となりうるということでした。彼は東京都老人総合研究所や北海道大学、東北大学の研究者に精力的に連絡をとり、免疫治療に応用する仮説を考え、その考察は彼ら研究者から高く評価してもらいました。進学は東京理科大学薬学部です。 No.12のGさんは地球温暖化と食糧問題の真実を知りたいと考えて研究を始めました。温暖化問題については、CO2温暖化説に対してその批判説、または批判的立場からの地球寒冷化説が入り乱れて主張を展開しており、まずその真偽を見極めようとしたのです。しかし、どの説も最後は推測であり、用いるデータはある地域限定のものであったり、推定モデルを根拠にしているもので、最後は彼女自身が何に着目するかをはっきりさせてからその立場から見てどちらのどの部分の主張に可能性が高いかで判断しました。また、食糧増産については、吹奏楽部員であり音楽好きな彼女らしく「植物がもつアミノ酸から発せられる波動とアミノ酸合成率の関係」を応用し、「植物ホルモンの受容体であるタンパク質の固有振動と関わる振動数を持つ音を流し、そのタンパク質を共鳴させて関連植物ホルモンを活発に受容させて成長を促進させる」という仮説を考察しました。実験で実証する時間がなかったので、進学先の筑波大学生命環境学群で実証するそうです。 ☆ お気づきかもしれませんが、No.5のCさんとNo.26のOさんの話は「その18」で紹介しました。二人とも早稲田大学に進学しました。Cさんは基幹理工学部、Oさんは先進理工学部です。 |
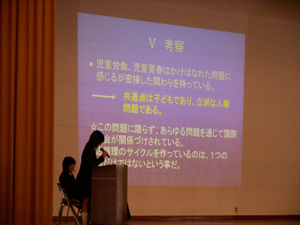
| 表-1 27回生 個人課題研究 田代ゼミ生の研究テーマ |
||
| No |
著者 |
研究テーマ |
1 |
A君 | 線維芽細胞増殖因子FGFについて |
2 |
B君 | ガンの免疫療法 |
3 |
Aさん | ガンの遺伝子治療におけるp53を用いた治療 |
4 |
Bさん | オジギソウについて |
5 |
Cさん | 住宅地と水田の適正配置によるヒートアイランドの緩和 |
6 |
Dさん |
川崎病における原因究明と治療展開 |
7 |
Eさん | 日本人の誇り |
8 |
C君 | 今の日本におけるホスピスの発展と小児ホスピスの実現 |
9 |
D君 | サヴァン症候群の発症原因について |
10 |
E君 | 暴力団対策法と現代のヤクザ問題 |
11 |
Fさん | アレルギーとこれからの治療 |
12 |
Gさん | 地球温暖化の検証および食糧問題解決への自分の仮説 |
13 |
Hさん | MAPC実用化への問題点と解決法 |
14 |
Iさん | 日本のODAの問題点と改善のための仮説と考察 |
15 |
F君 | 新型インフルエンザウィルス~問題点とその解決策~ |
16 |
G君 | 公訴時効の正義性を考える |
17 |
Jさん | 自分の犬の問題行動を動物行動学から考える |
18 |
Kさん | 脂肪細胞を小さくする |
19 |
Lさん | 動物の寄生虫 |
20 |
Mさん | ペンギンの生態と歴史について |
21 |
H君 | A~G型肝炎の特徴を理解し、難治性のB型・C型について考える |
22 |
I君 | 腫瘍エスケープ機構を考慮に入れた新免疫療法 |
23 |
J君 | 糖鎖科学の研究の現状と疾患に対する有用性 |
24 |
K君 | 日本銀行と欧州中央銀行の比較 |
25 |
Nさん | 日米安全保障条約および事前協議制と核に関する密約 |
26 |
Oさん | 体性幹細胞による再生医療 ~体性幹細胞を用いたティッシュエンジニアリングによる人体再生と体性幹細胞の可能性~ |
27 |
Pさん | テーラーメイド医療~個人差の原因である遺伝子多型と解析法~ |
28 |
L君 | ニューロン新生メカニズムを利用した末梢神経障害治療 |
29 |
M君 | 水素化・メタノール化による二酸化炭素の削減 |
30 |
N君 | 希望の癌治療 |
31 |
Qさん | 動物実験の現状と代替法の可能性 |
32 |
Rさん | 児童虐待が脳に及ぼす影響~海馬の萎縮に対する新療法を考える~ |
33 |
Sさん | 有機ELディスプレイについて |
34 |
O君 | リスクをどう回避するか |
35 |
P君 | 漢方と西洋医学の併合 |
36 |
Tさん | トランスジェニック技術の開発 |
37 |
Uさん | 早老症について |
38 |
Vさん | 世界的教育援助ネットワークを考える |
39 |
Wさん | イラク戦争問題と復興人道支援を世界的視点から考える |
|
筆者 : 自己紹介 |
|||||
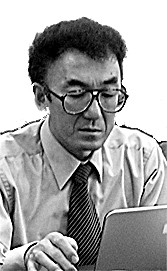 |
茗溪学園中学校高等学校 教務部長 広報・入試係 化学の教師です。 茗溪学園では前向きで明るく逞しく積極的な青年が育っています。 「有名大学に行きたいから勉強する」のではなく、「中学・高校時代にいろいろな事に挑戦し、失敗し、考え、自分を探して、自分で自分の将来をみつけ、自分で歩んでいく。その方向が地球を救い、人類の未来を拓く方向であってほしい。」そう考え、支援するのが茗溪学園の教員の役割です。 海外生・帰国生が自分の力で自分の未来を切り拓いてきた経験はここで開花します。これまでたくさんの帰国生が、夢を追いながら進学していく姿を見て応援してきました。 よろしくお願いします。 茗溪学園の「Study Skills」やカリキュラムについてのご質問は、 |
||||